給与所得控除とは?令和7年分から控除額が変わる!?年末調整に向けて足立区の税理士が徹底解説!
- hsatou0
- 2025年11月7日
- 読了時間: 4分
給与所得控除は、会社員などで給与収入を得ている人を対象に、必要経費に相当する金額を給与収入から差し引く制度です。
年末調整においてこの"給与所得控除"の仕組みは非常に重要で、基礎控除と同様に必ず理解しておく必要があります!
また、令和7年税制改正で控除額の見直しもあり、年収の壁にも影響してきます。
どんな人が対象なのか?控除額はいくらなのか?年末調整や確定申告に向けて税理士が徹底解説します!
1 . 給与所得控除とは?

給与所得控除とは、会社員などで給与収入がある"給与所得者"全員を対象として、必要経費に相当する金額を給与収入から差し引くことができる制度です。
自営業者などの個人事業主は、実際にかかった経費を収入から差し引けるのに対し、給与所得者は経費を個別に申告できないため、一律に認められた『みなし経費』としての役割となっています。
これにより、経費を申告できない給与所得者の税負担の軽減に繋がっています。
他の所得控除(基礎控除や配偶者控除など)は個人事業主も含む全ての人が対象になるのに対し、給与所得控除は給与所得者のみに適用される点に違いがあります。
また、年末調整や確定申告の際によく確認される『所得』とは、給与収入からこの給与所得控除を差し引いた後の金額を指します。
2 . 適用する為の手続きは?

給与所得控除は全ての給与所得者に自動で適用されます。
他の所得控除と違い基本的には自動適用されるので、特別な手続きは必要ありません。
年末調整を行っていれば、自動で適用された上で税金計算がされ、源泉徴収票には給与所得控除が差し引かれた後の所得金額も記載されています。
(詳しくはこちらの記事をご覧ください。)
ただし、退職時の源泉徴収票には給与所得控除の金額は反映されていません。
(年末調整をしないと給与所得控除の金額が確定しない為)
年の途中で退職をし自身で確定申告を行う場合は、自分で給与所得控除の金額を計算し、確定申告書に記載をする必要があります。
ですが、オンラインの国税庁の確定申告書作成コーナーで申告書を作成する場合は、源泉徴収票の給与収入の金額を入力すれば自動で給与所得控除の金額も算出されます。
紙で手書きで作成する場合だけ注意しましょう。
3 . 給与所得控除の金額は?
令和7年税制改正により、給与所得控除の金額が見直されました。
最低控除額が55万円だったのに対し、改正により最低控除額が65万円に引き上げられています。
給与収入の金額(額面) | 給与所得控除額 |
1,900,000円まで | 650,000円 |
1,900,001円から 3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円から 6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円から 8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
給与収入の金額によって控除額が分けられていて、収入が8,500,001円以上になると、控除額は上限の1,950,000円に達します。
つまり、給与所得者は誰でも65~195万円をみなし経費として控除することができるのです。
ちなみに、給与収入が65万円以下の人は『所得』は0円となります。
(収入を給与所得控除で引ききってしまう為)
4 . 控除額が引き上げられてどう変わる?

令和7年度税制改正により、給与所得控除の金額が最低55万円から最低65万円へと引き上げられました。
最低ラインが引き上げられただけの為、この改正により影響を受けるのは、給与収入が190万円未満の人です。
(給与収入が190万円超の人は改正後でも控除額に変わりはありません。)
これにより、いわゆる年収の壁の103万円も引き上がることになり、給与収入が160万円以下であれば本人の所得税が発生しないラインとなります。
(給与所得控除と同時に基礎控除の引き上げも行われています。詳しくはこちらの記事をご覧ください。)
103万円を超えても160万円までであれば所得税が発生しない範囲で働くことが可能になりました。
具体的には、今までは給与収入150万円の人は23,500円の所得税が発生していましたが、令和7年分は所得税が0円となります。
5 . まとめ
給与所得控除は所得控除の中でも性質が異なり、給与所得者全員が対象となる基本的な所得控除です。
令和7年度税制改正により控除額が引き上げられている為、確定申告や年末調整の際は計算ミスがないように心がけましょう。
また、『所得』とは給与収入から給与所得控除を差し引いた後の金額となりますので、収入と所得を混同しないように注意しましょう。
その他、所得控除等について分からないことがあれば、お近くの税理士にご相談ください。
ご相談の方は以下よりお問い合わせください。
初回は相談無料となります。
※上記記事は令和7年11月時点の情報に基づいて記載しております。
※上記記事は一般的な内容を記載しているため判断の際は専門家へのご相談をお願い致します。
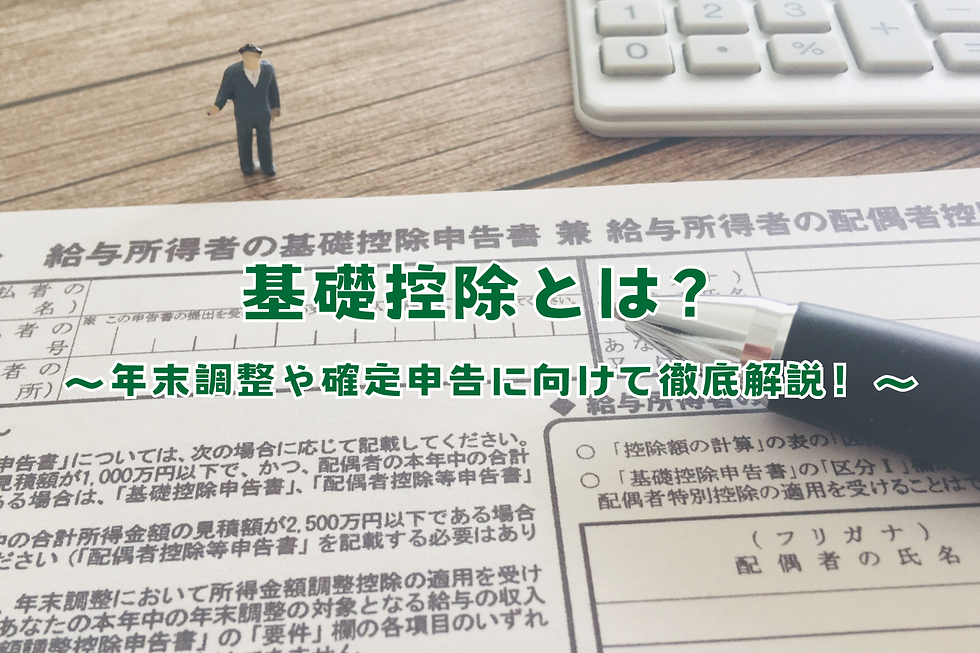

コメント