160万円の壁に決定。給与所得控除と基礎控除を理解して税負担について考えよう!足立区の税理士が解説!
- hsatou0
- 2025年5月2日
- 読了時間: 5分
毎年、税制は少しずつ変わりますが、2025年も給与所得者にとって大切な控除額が決まりました。税金対策を考えるうえで、給与所得控除と基礎控除は非常に重要な要素です。これらを適切に理解し、上手に活用することで、税負担を軽減できる可能性があります。
今回は、2025年版の給与所得控除と基礎控除の早見表を使って、各年収帯ごとの控除額をチェックし、どのように税金の負担が変わるのかを見ていきましょう。
※所得税のみに絞ったブログとなっております。住民税等については触れていません。
目次
1. 2025年版|年収別 給与所得控除+基礎控除 早見表
2. 給与所得控除と基礎控除とは
3.年収別の税額早見表で税負担をチェック
4.年収別に見る税額の例
5.まとめ
1.【2025年版|年収別 給与所得控除+基礎控除 早見表】

年収(目安) | 給与所得控除額 | 基礎控除額 |
〜190万円未満 | 65万円(定額) | 95万円(58+37) |
190〜200万円未満 | 年収×30%+8万円 (65万円〜68万円) | 95万円(58+37) |
200〜360万円未満 | 年収×30%+8万円 (68万円〜116万円) | 88万円(58+30) |
360〜475万円未満 | 年収×20%+44万円 (116万円〜139万円) | 88万円(58+30) |
475〜665万円未満 | 年収×20%+44万円 (139万円〜177万円) | 68万円(58+10) |
665〜850万円未満 | 年収×10%+110万円 (176万円〜195万円) | 63万円(58+5) |
850万円以上 | 195万円(定額) | 58万円(固定) |
※年収2400万円以上の場合は控除額が変わります。
2.給与所得控除と基礎控除とは

所得税額は、収入(いわゆる年収)から給与所得控除と基礎控除、その他控除を引いた結果算出される課税所得によって決定されます。 課税所得が小さい程、税負担は軽減されます。つまり、これら控除の金額が大きいほど、減税されるということです。
給与所得控除とは、給与所得者が税金計算をする際に認められる控除額です。これは、給与が多くなるほど控除額も増える仕組みになっています。
基礎控除は、ほぼすべての納税者に一律で適用される控除額で、一定額(58万円)が控除されます。そして、2025年は年収が低い程控除額が増加する仕組みになっています。
たとえば、年収が190万円未満の場合、給与所得控除は65万円(定額)、基礎控除は95万円(58+37)となり、最も手厚い控除を受けることができます。これにより、課税対象額が大きく減少し、実際の税負担が軽減されることになります。
※給与所得控除は65万円(定額)、基礎控除は95万円(58+37)を足した金額が160万円となり、所得税が0円となる年収(その他各種控除については度外視)のため、「160万円の壁」と呼ばれます。
・年収に応じた控除額の変化
年収が増えると、控除額の内容が少しずつ変わります。たとえば、年収200〜360万円未満の場合、給与所得控除は「年収×30%+8万円」となり、金額にして68万円〜116万円となります。一方で、基礎控除は88万円(58+30)に設定されており、この年収帯でも比較的大きな控除が受けられます。
・高所得者への影響
年収850万円以上の高所得者の場合、給与所得控除は195万円(定額)となり、基礎控除は58万円(固定)と、両方とも上限が設定されています。
※年収2400万円以上の場合は控除額が変わります。
3.年収別の税額早見表で税負担をチェック

次に、実際の税額早見表を見てみましょう。この表は、年収ごとの給与所得控除、基礎控除、課税所得、そしてその結果として支払う所得税額を示したものです。
※社会保険料控除等、各種控除を度外視しているため、実際の所得税額は下記表の金額よりも減少することが予想されます。また、復興特別所得税(所得税額に対して2.1%の課税)も加味しておりません。
年収(万円) | 給与所得控除(万円) | 基礎控除(万円) | 課税所得(万円) | 所得税額(円) |
160 | 65 | 95 | 0 | 0 |
200 | 68 | 88 | 44 | 22,000 |
300 | 98 | 88 | 114 | 57,000 |
400 | 124 | 88 | 188 | 94,000 |
500 | 144 | 68 | 288 | 190,500 |
600 | 164 | 68 | 368 | 308,500 |
700 | 180 | 63 | 457 | 486,500 |
800 | 190 | 63 | 547 | 666,500 |
900 | 195 | 58 | 647 | 866,500 |
1,000 | 195 | 58 | 747 | 1,082,100 |
1,200 | 195 | 58 | 947 | 1,591,410 |
1,400 | 195 | 58 | 1,147 | 2,249,100 |
1,600 | 195 | 58 | 1,347 | 2,909,100 |
1,800 | 195 | 58 | 1,547 | 3,569,100 |
2,000 | 195 | 58 | 1,747 | 4,229,100 |
※社会保険料等を考慮したい場合:
源泉徴収票に記載のある社会保険料額を課税所得覧の金額から引いた金額に税金がかかります。
例えば、年収600万円で社会保険料として80万円を負担している場合は、368万円(年収600万円の課税所得)-80万円=288万円となり、所得税額は190,500円となります。
所得税の計算には下記、国税庁のHPを参考にしています。
4.まとめ

2025年の税制改正において、給与所得控除と基礎控除は税負担に大きな影響を与える要素となります。年収帯ごとの控除額を理解することは、単に税金を減らすためではなく、自分自身の税負担がどのように変動するかを見極めるための重要なステップです。
給与所得控除と基礎控除は、年収が異なれば適用される額も変わります。特に低年収の人々にとっては、大きな控除を受けることで実際の税負担が軽減されることがわかります。一方で、高年収者の場合、控除額に上限が設けられ、税負担の軽減効果は低くなることもあります。
このブログを通じて、税負担について改めて考えるきっかけを持っていただけたでしょうか。年収が変動する中で、控除の変化により税金の負担がどのように変わるかを理解し、しっかりと把握しておくことが、将来的な税制改正に適応するためにも重要です。自分の年収に応じた控除額を確認し、税金対策を意識して生活設計を行うことが、健全な財務管理への第一歩です。
税負担の変動を理解し、今後の給与や収入に対する適切な対応策を考えることが、賢い税金管理をするための基本となります。
また、次回のブログでは国民民主党案の基礎控除(いわゆる178万円の壁)が採用されていた場合、現行の税制と比較してどれだけ減税の効果があったかについてを解説します。ぜひご覧ください。
ご相談の方は以下よりお問い合わせください。
初回は相談無料となります。
※上記記事は令和7年4月時点の情報に基づいて記載しております。
※上記記事は一般的な内容を記載しているため判断の際は専門家へのご相談をお願い致します。

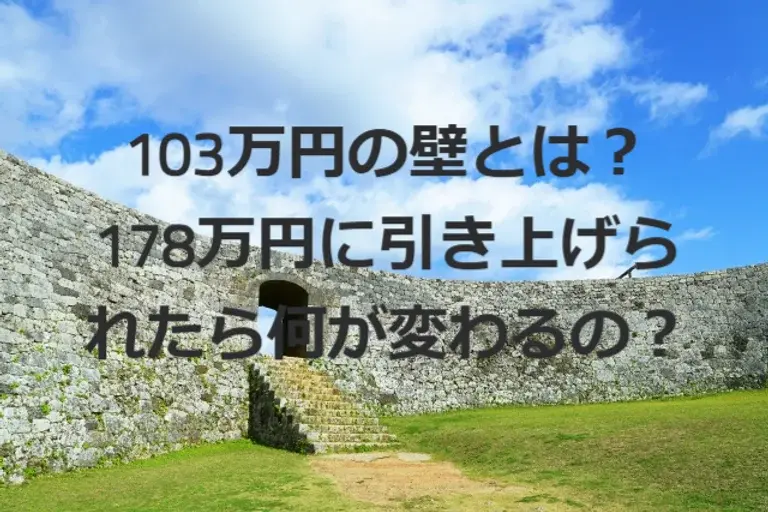
コメント